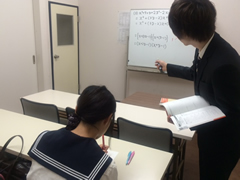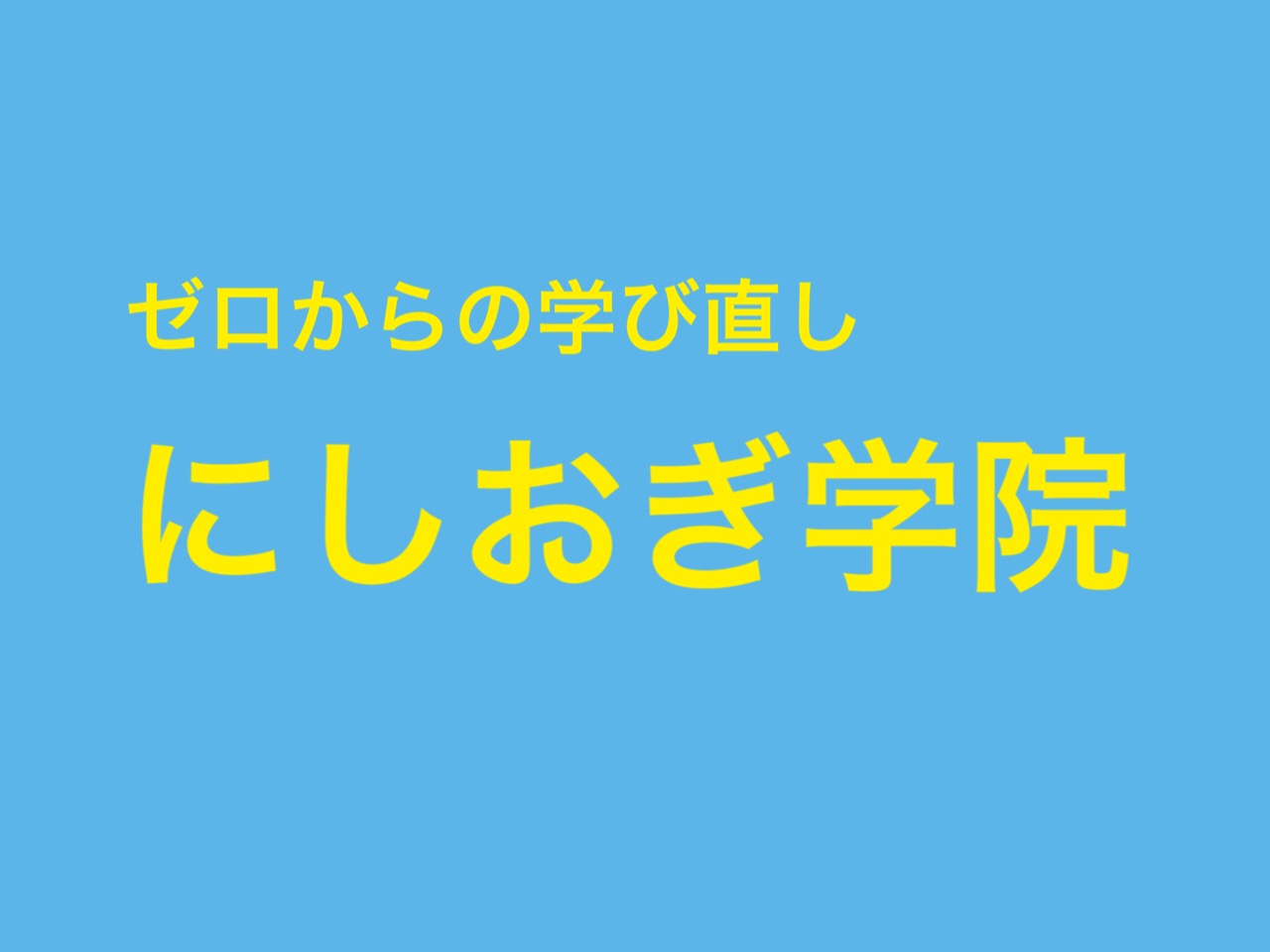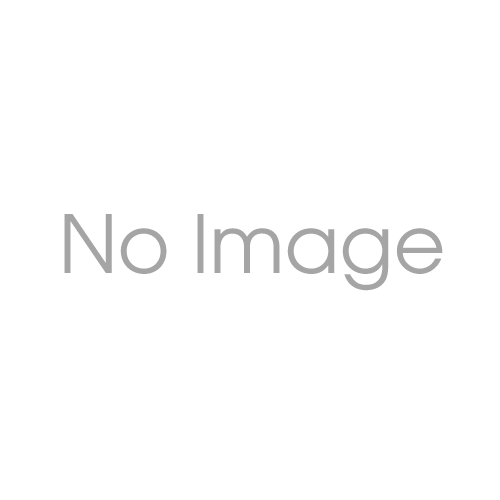不登校・ひきこもりと睡眠障害④〔睡眠時のホルモン分泌〕
管理者用
ホルモン分泌と睡眠・覚醒の関係
私たちの概日リズムや睡眠サイクルは、ホルモン分泌と密接な関係があります。
不登校・ひきこもりなどが常態化することで、生活リズムが崩れて不規則になりがちになると、睡眠・覚醒に関係するホルモン分泌もその影響を被ることになってきます。
1.ノンレム睡眠時の成長ホルモン分泌
前回の記事ではノンレム睡眠とレム睡眠の交互の繰り返しによる睡眠サイクルについて、前々回までの記事では24時間周期と概日リズムについて述べてきました。
今回は睡眠サイクル(ラム・ノンレムの相互サイクル)や概日リズム(生物時計)によって生じてくるホルモン分泌について述べたいと思います。
特に思春期の子どもの成長にとって最も大切なホルモンのひとつが成長ホルモン(グロースホルモン)です。
成長ホルモンは、最初のノンレム睡眠の際に一晩に放出される全体量の7~8割が分泌されます。前回記事でも触れましたが、最初のノンレム睡眠は約3時間ですが、その前半の90分で入眠に失敗した場合、成長ホルモンの分泌量を大幅に減らしてしまうことになるのです。
成長期・思春期の子どもが就寝時間の眠気を我慢してスマホゲームに興じることは非常に危険であると言わざるを得ません。
成長ホルモンの十分な分泌のためには熟睡が必要不可欠であり、就寝前のスマホ使用には注意が必要なのです。
2.睡眠時に分泌される脳下垂体ホルモン
睡眠による疲労回復には、睡眠時に分泌される特有のいくつかのホルモンと密接な関係があります。
ここでは先ず脳下垂体から睡眠時に分泌される主要なホルモンについてまとめておきたいと思います。「脳下垂体」とは脳の直下にあって様々なホルモンを分泌する内分泌器官です。
脳下垂体から分泌されるホルモンは成長や出産時など一定の期間に大きく身体を変化させる作用をするだけでなく、ヒトの生涯を通じてその過不足が健康状態に大きな影響を及ぼすといわれるきわめて重要なホルモンです。
【睡眠時に分泌される主な脳下垂体ホルモン】
①成長ホルモン
②プラクチン
③甲状腺刺激ホルモン
④黄体形成ホルモン
⑤副腎皮質刺激ホルモン
これらの中で、「睡眠時にしか」分泌されないホルモンは、①~④です。なお③の甲状腺刺激ホルモンの分泌は、睡眠と概日リズムの両方の影響を受けています。
3・不登校・ひきこもりで乱れる睡眠サイクル
成長ホルモンの分泌は覚醒時には見られず、最初のノンレム睡眠時の熟睡状態時に大半が一気に放出されます。成長ホルモンを放出させる物質は、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を誘発する睡眠物質と同時に分泌されます。
夜更かしや徹夜などで睡眠の時間帯(睡眠相)を後ろにズラしていくと、深いノンレム睡眠を確保することができなくなり、成長ホルモンの分泌量は全体的に大幅に低下します。
夜間睡眠が途切れ途切れになっても、成長ホルモン分泌のピーク値は低下することが知られています。
つまり、思春期に睡眠のとり方が不規則なると成長に悪影響を及ぼしかねないということです。
不登校やひきこもりの期間中にスマホ依存やゲーム障害に陥り長期化すると、就寝・起床の時間帯が不規則になっていくことが少なくありません。「食べたいときに食べ、寝たいときに寝る」という生活をしていると、夜間睡眠が分断化されやすい状態になっていきます。
この結果、ノンレム睡眠による熟睡状態を確保できず全体的な成長ホルモンの放出量が減ることになります。思春期であるにもかかわらず、十分な成長ホルモンを確保できなくなるのです。
4.黄体形成ホルモンについて
黄体形成ホルモンは、性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)の一種であり、第二次性徴の始まる思春期に分泌量が増加するホルモンです。
また黄体形成ホルモンは、思春期に限って「夜間睡眠時」のみに分泌されることが知られています。
成長途上にある思春期の子どたちは、この第二次性徴の時期に夜間睡眠不足に陥った場合、先述した成長ホルモンだけでなく、性ホルモンまでもが不足することになるのです。
黄体形成ホルモンは、具体的には男性ならば精巣、女性なら卵巣といった生殖腺に直接働きかけて性ホルモンの分泌を促進します。
夜間睡眠を軽視すると、身体の成長だけでなく性的な成熟も妨げられることになるということです。
この意味においても、やはり思春期における安定した夜間睡眠の確保はきわめて重要であると言わざるを得ません。
思春期に夜間睡眠を確保しなければ成長が阻害されることになるのです。
5.概日リズムの影響を受けるホルモン分泌
概日リズム(生物時計)の影響下にあって、睡眠に関連して分泌されるホルモンも存在します。
①副腎皮質⇒コルチゾール
②松果体⇒メラトニン
③脳下垂体⇒副腎皮質刺激ホルモン
①のコルチゾールは分泌が減少するにしたがって、深いノンレム睡眠が訪れます。②のメラトニンは24時間周期で産生されていますが、分泌は夜間に限定され睡眠圧(眠気)を増進させる役割があります。③の副腎皮質刺激ホルモンは、コルチゾールを分泌させるホルモンで、副腎皮質刺激ホルモンとコルチゾールはほぼ同調して分泌されています。
6.メラトニンとコルチゾール
メラトニンは概日リズムに支配されるホルモンですが、脳内の松果体において24時間周期で産生され、夜間に血液中に放出される睡眠物質です。
メラトニンは日没ごろの時間帯に血液中に分泌され、日の出とともに消失します。強い光を浴びるとメラトニンは消失し、脳も身体も覚醒していきます。
夜間はメラトニンの放出時間が長いため深い眠りが持続しますが、逆に放出時間が短くなる明け方だと次第に眠りにくい状態になっていきます。
明け方近くになるとメラトニンの分泌量が減少していき、覚醒時にはコルチゾールの分泌量が増大していきます。
概日リズムと24時間周期のズレを修正しリセットする働きがあるため、メラトニン自体が概日リズム睡眠障害の治療にも用いられます。
またメラトニンは、精神状態を鎮静化させる作用があるため、抗うつ剤としての利用も進んでいます。
7.スマホによる夜更かしは有害です
スマホによる夜更かしが概日リズムによるホルモン分泌に逆行するものであることはすでに述べたとおりです。
夜通しスマホに興じて明け方近くに眠りについたとしても、熟睡することは非常に難しいと言わざるを得ません。
概日リズムに従って深夜にはメラトニンの分泌量がピークを迎え、明け方に向けて減少していきます。
つまり、眠りにつくときには脳は睡眠から覚醒に向かっていく時間帯に入っていくのです。
そして深い眠りにつくことに失敗すると、前述の脳下垂体ホルモンの分泌が大きく阻害されることにつながります。
スマホによる夜更かしは、健康的な睡眠を得るためにいいことは何もないということです。
8.次回は「睡眠障害の分類」です
今回の記事では、睡眠サイクルの影響下になる脳下垂体ホルモンの分泌、概日リズムの影響を受けるメラトニン、コルチゾールについてまとめました。
次回の記事では、睡眠障害の分類について扱いたいと思います。
これまで扱ってきた概日リズム睡眠障害のほかにも、睡眠障害の病態は多様であり分類は多岐に渡ります。
今回記事の参考文献は以下の通りです。
【参考文献】50音順
・子どもの睡眠ハンドブック(駒田陽子・井上雄一編,朝倉書店)
・小児科臨床ピクシス14睡眠関連病態(五十嵐隆総編集,中山書店)
・睡眠障害の子どもたち(大川匡子編著,合同出版)
・ニュートン式超図解最強に面白い!!睡眠(柳沢正史著,ニュートンプレス)
・脳とホルモンの行動学〖第2版〗(近藤保彦他編,西村書店)
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)