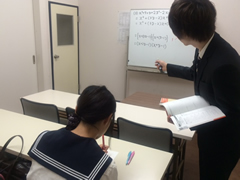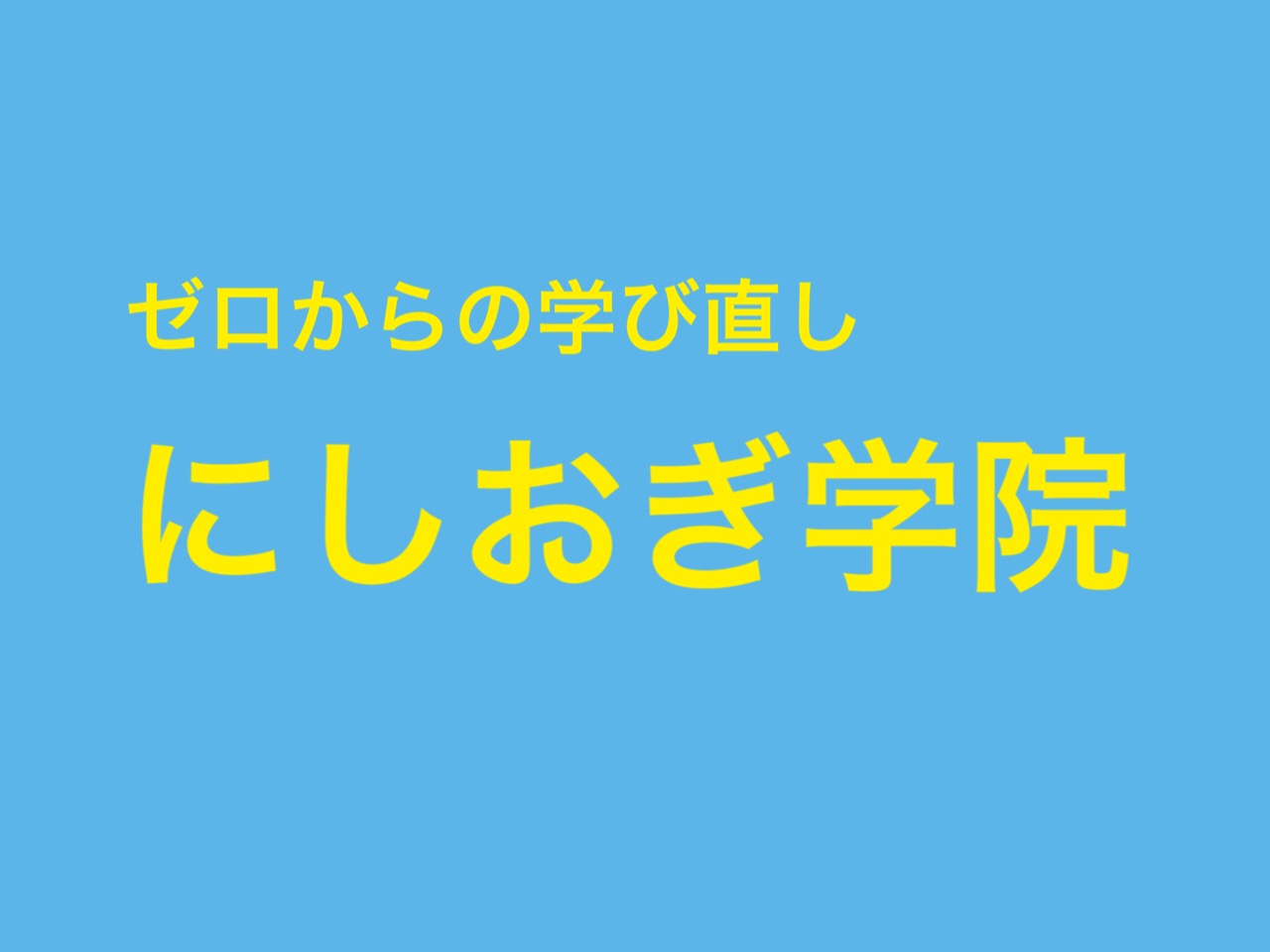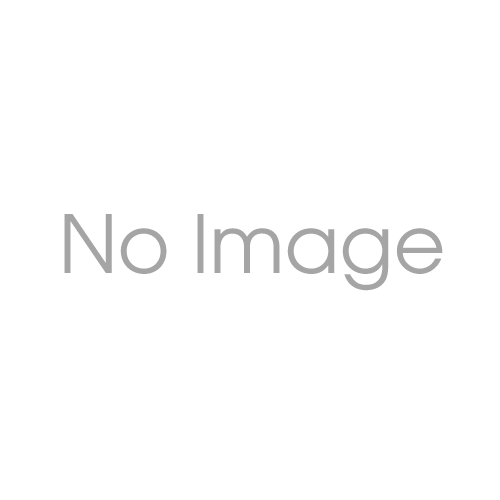不登校・ひきこもりと睡眠障害②〔一斉臨時休校と概日リズム睡眠障害〕
管理者用
一斉臨時休校と睡眠障害について
日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中、2020年2月27日に安倍晋三首相(当時)の要請により、3月から順次全国で一斉休校が広がりました。
同年4月7日に初めての緊急事態宣言が発出されることになり、一斉休校は5月下旬まで延長されることになりました。そして学校が再開されて以降、不登校が急増し始め、現在も増え続けています。約3か月間の休校期間中に、子どもたちの規則正しい生活リズムが崩れ、睡眠・覚醒リズムに変調を来しやすくなったとしても不思議ではありません。
今回の記事では、昼夜逆転に起因する「概日リズム睡眠障害」と「一斉臨時休校」を軸に述べさせていただきます。
1.概日リズムは前後にそれぞれズレます
前回の記事「不登校・ひきこもりと睡眠障害①〔昼夜逆転の仕組み〕」でも触れたように、概日リズムと24時間周期のズレが修正されないまま放置されると、ヒトは簡単に昼夜逆転してしまいます。
概日リズムが24時間周期に同期されるためには、朝日によるリセットが必要です。
網膜が朝の日光を浴びると、視床下部にある視交叉上核に情報が伝達されます。
これによって、概日リズムと地球の自転周期が同期されることになりリセットされます。
起床後にすぐカーテンを開けて朝の日の光を浴びることは、覚醒するためには生物学的にも非常に理にかなったことだと言えます。
2.長期間の一斉臨時休校や外出自粛でスマホ漬けに
国際基準による睡眠障害の分類は3つの項目に大別されますが、これらのうちの1つが「概日リズム睡眠障害」です。
10代の中高生に限って言えば、深夜から明け方にかけてのスマホの長時間にわたる利用などにより増加傾向にあると考えられます。
昼夜の区別なくスマホでゲームや動画視聴にのめり込むことで、固有の体内時計を破壊してしまうこともあります。
特に2020年春の一斉休校(臨時休校)や、その後の緊急事態宣言発出による外出自粛要請により、家の中で一人で過ごす時間が増え、やることがないから一日中スマホをいじっていたという中高生は少なくありません。
登校時間や部活などの時間的な制約に左右されず生活できたとも言えますが、そのことと引き換えに体内時計に異常を来してしまい、一斉休校・緊急事態宣言が解除されてからも概日リズムと24時間周期のズレをリセットできないまま不登校・ひきこもりに陥ってしまったという生徒もたくさんいるようです。
2020年以降、不登校の数が急増していますが、睡眠障害に悩まされている子どもたちは実は非常に多いのではないでしょうか。
3.概日リズム睡眠障害の7つの分類
概日リズム睡眠障害は次の7つに分類されています。
①ジェット時差(時間帯域変化)症候群
②交代勤務睡眠障害
③睡眠相後退症候群
④睡眠相前進症候群
⑤不規則型睡眠・覚醒パターン
⑥非24時間型睡眠・覚醒障害
⑦特定不能の概日リズム睡眠障害
⑥の「非24時間型」は「非同調型」とも言われ、入眠時刻と覚醒時刻が毎日1時間ずつ遅れていきます。このタイプの場合、試験など大切な用事があったとしても、自分の意思では起床できないという特徴があります。
中高生の不登校・ひきこもりにおいて特に重要なのは、③~⑥のタイプではないでしょうか。この記事ではその中でも③と④に焦点化して、一斉休校期間中のスマホ依存の観点から概日リズム睡眠障害について考えてみたいと思います。
4.思春期に多い夜更かし型の「睡眠相後退症候群」
③と④は、主睡眠となる時間帯が前後に大きくズレてしまい、そのまま常態化されたことによって起きる疾患です。
③は思春期に発症することが多く、いわゆる「夜更かし型」の睡眠障害であるといえます。また、相対的に女子より男子の方が発症率が高いといわれています。
中高生の不登校・ひきこもりの問題を考える上で、まず重要なのは夜更かし型の「睡眠相後退症候群」の方です。睡眠相後退症候群では、概日リズムがリセットされず遅れたままになっています。
この場合、明け方にならないと入眠できず昼過ぎにならないと起床することができません。
この症状に関しては、不登校・ひきこもりに陥っている中・高生の中には、思い当たる節のあるという人は多いのではないでしょうか。というより、むしろ一斉休校や厳しい外出自粛要請によって自宅に待機するしかなかったあの時期に、この睡眠リズムになってしまった人が多いのは当然なのかもしれません。
この問題について、スマホのブルーライトとの関係を通してさらに検討してみたいと思います。
5.就寝前のスマホは時間を巻き戻す
すでに繰り返し述べてきたように体内時計の中枢は視交叉上核にありますが、この中枢以外にも、全身の他の細胞にも体内時計の機能を持つ細胞が存在しています。
これらは視交叉上核の中枢時計と区別して「末梢時計」と呼ばれています。概日リズムが毎朝リセットされると、中枢時計から末梢時計に伝達されています。
目の網膜には光を感知する視細胞が並んでいて、これら視細胞が感知した信号を脳へ中継するのが網膜の神経節細胞です。
この神経節細胞の一部が、およそ波長460ナノメートルのブルーライトを感知して、視交叉上核にある体内時計の機能を調節しています。
スマホが発光しているブルーライトは体内時計にダイレクトに影響を与えており、就寝前の深夜などにこの光を浴びてしまうと、概日リズムが1~2時間程度巻き戻されてしまうことが分かっています。つまり入眠時間が単純に1~2時間遅くなってしまうことになるのです。
このため睡眠相が後退しやすくなると考えられますが、入眠時刻のどんどん後退していくと明け方まで眠れなくなります。
ゲームのオンライン化が短時日で急激に進んで常態化した上、現在のオンラインゲームの6割強がスマホゲームで占められているということに関して、周囲の大人たち(親や教師)は十分な注意が必要です。しかし、一斉休校、緊急事態宣言、外出自粛要請という異常な状況の中で、子どもにとって唯一のよすがであるゲームや動画視聴に強い制限をかけることは容易なことではなかったと推察されます。端的にいえば、時間つぶしの手段が他になかったということです。
6.「睡眠相前進症候群」について
後退症候群とは逆に、極端な早寝をしてしまうと体内時計が前にズレてしまい、夜まで起きていられなくなります。
これは不登校の中高生から時々耳にすることですが、夕方の5~6時頃にうとうとと眠ってしまい、目が覚めたら夜中の2時~3時ごろだったということがあるようです。
睡眠相前進症候群は、一般的には入眠時刻が午後6時~8時で覚醒時刻が午前1時~3時であるといわれていますが、体内時計が太陽リズムの24時間周期に同調するためのリセット機能が正常に働かなくなることで生じる概日リズム睡眠障害であることは間違いありません。
不登校やひきこもりの場合、そもそも学校のタイムテーブルに縛られることがないため、外的な制約から自由な分、寝たいときに寝て起きたいときに起きるという睡眠習慣に陥りがちです。特に保護者が仕事で帰宅時刻が遅いなどの場合、さらにこのような傾向が強くなるのかもしれません。
しかし、このような極端な早寝の習慣が続くと睡眠リズムがこのまま固定されてしまいます。いくら「早寝早起き」の習慣がいいからといっても限度があるのです。
不登校の生徒で、うちの塾の夜8時の授業でも起きられず間に合わないという場合は、このパターンが多いのは事実です。この生徒たちは「昼寝」や「仮眠」のつもりで夕方ごろから寝ているようですが、後で聞いてみると自然に目が覚める時刻は午前1時過ぎだと言っていました。本人が気づかないうちに、睡眠相が大幅に前進してしまっている可能性があるということです。
つまり本人にとっては「主睡眠」のつもではなく、あくまで「仮眠」のつもりだといういうことが重要なポイントです。
7.一斉臨時休校を契機とした概日リズムの攪乱
実際に不登校・ひきこもりが長期化する中高生がコロナ禍以降は増えていますが、こうした子どもたちの多くは一日の中でスマホに費やす時間が増大し、その結果として昼夜逆転した生活リズムが固定化されていくことになります。
もちろん一斉臨時休校も、緊急事態宣言に基づく外出自粛要請も、疫学的な感染予防の観点から新型コロナウイルスのパンデミックを抑止するためにはやむを得ませんでした。
しかし思春期の時期に数ケ月にわたる一斉休校によって自宅待機を強いられ、はからずも「スマホ漬け」「ゲーム漬け」になってしまった子どたちは少なくないのではないでしょうか。つまり感染予防とは別の側面で、子どもたちの心身が蝕まれてしまっということは否定できない事実であろうと思われます。
実際に一斉休校が解除された後も睡眠リズムが戻らなかった生徒たちに話を聞いてみると「友達にも会えないので、スマホで時間を潰すしかなかった」「登校時刻を気にしなくていいから、すぐに昼夜逆転した」「寝る時間や起きる時間が無茶苦茶になった」「一斉休校が早めに明けると知ったので生活リズムを直そうとしたが戻らなかった」という反応が返ってきますが、これらは考えてみると自然な成り行きなのではないでしょうか。
今後も新たな感染拡大が起きる可能性は否定できません。その場合には、感染予防と子どもの睡眠衛生について、子どものスマホ利用と概日リズムの両面で改めて検討していく必要があるといえるでしょう。
睡眠障害はいったん罹患すると寛解に時間がかかることが少なくありません。このため、子どものキャリア形成に深刻な影響を与えますし、最悪の場合は子どものキャリア形成を途絶しかねないと認識しておくべきなのです。子どもにとって睡眠障害によって失われる数ケ月は、大人が考える以上に子どもの人生設計に深刻な影響を及ぼしかねないということです。
8.次回では睡眠サイクルについて取り上げます
これまでは概日リズム(サーカディアンリズム)と24時間周期のズレの問題を検討してきました
次回の記事では、主に『スタンフォード式 最高の睡眠』(西野精治著,サンマーク出版)の内容に依拠しながら、睡眠中の睡眠サイクルについて取り上げる予定です。
睡眠サイクルとは、具体的にはレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルを指します。
なお今回記事の参考文献を列挙しますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【参考文献】50音順
・子どもの睡眠ハンドブック(駒田陽子・井上雄一編,朝倉書店)
・小児科臨床ピクシス14睡眠関連病態(五十嵐隆総編集,中山書店)
・睡眠の科学(櫻井武著,講談社)
・睡眠障害の子どもたち(大川匡子編,合同出版)
・脳とホルモンの行動学(近藤保彦他編,西村書店)
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)