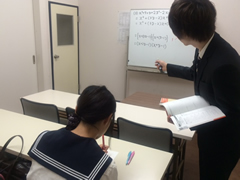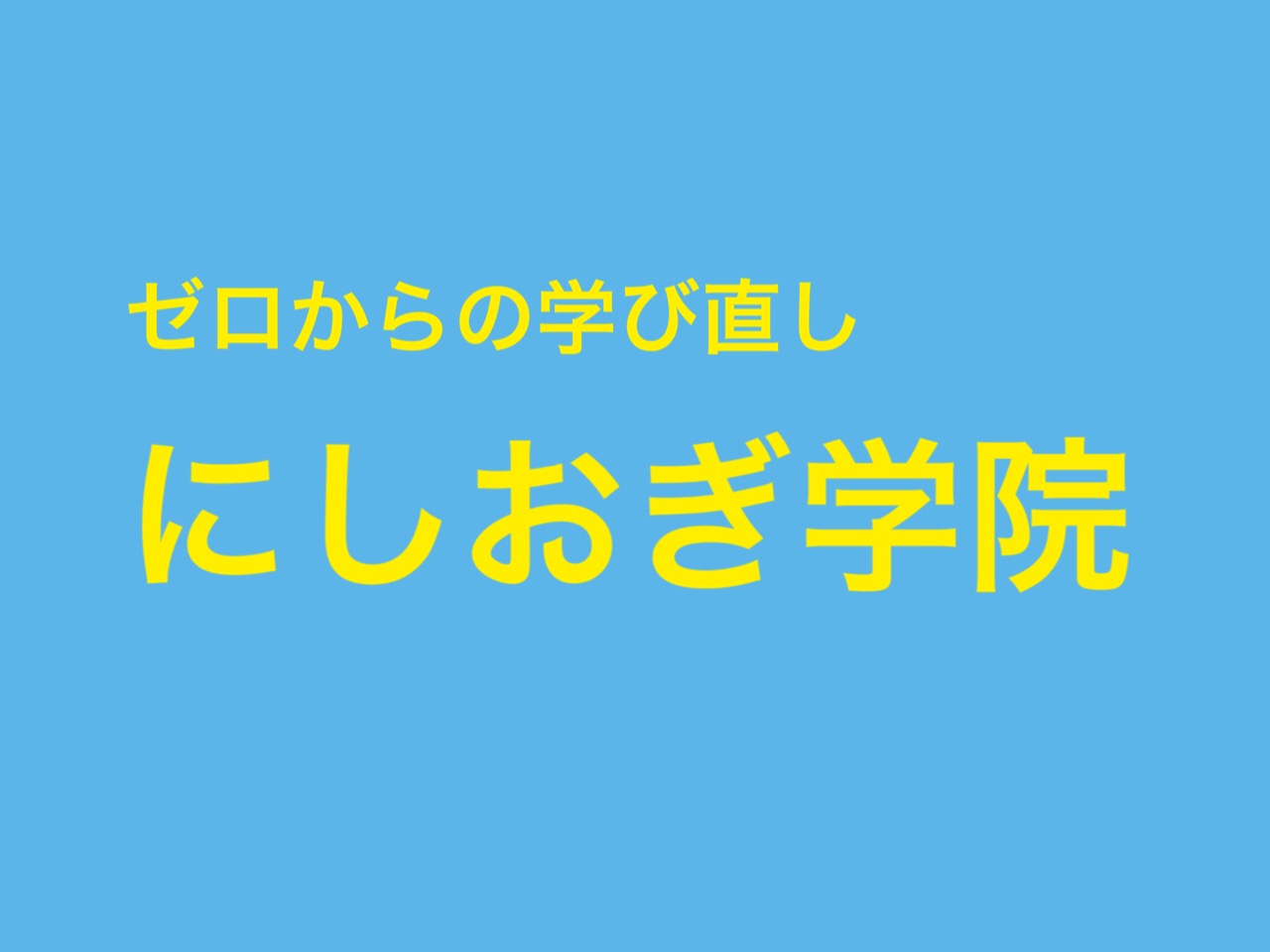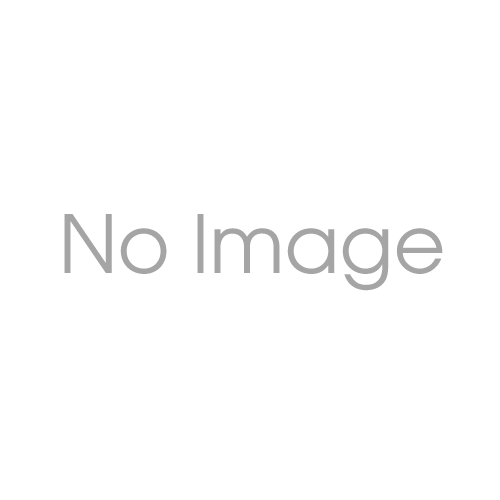不登校・ひきこもりと不安障害について⑥〔社会(社交)不安障害と思春期〕
管理者用
社会(社交)不安障害は成功体験の機会を奪います
社会(社交)不安障害〔SAD〕の生徒は、自分が他人にどう見られているかを過度に気にしています。
そしてSADに特徴的なのは、緊張によって生じる身体症状よりも、緊張している自分の不安を周囲に悟られることに恐怖を感じるということです。
人前でのミスを経験すると、それがきっかけでますます人前に出られなくなり、本人が苦手だと感じる場面・場所には容易に出て行けなくなります。
こうして回避行動をとりがちになりますが、この回避行動によって、かえって不安を強めてしまうことになり、悪循環に陥ることになるのです。
この悪循環にはまってしまうと、不登校・ひきこもりの生活になり、授業を受けることも試験を受けることもできなくなってしまい、成功体験の機会が奪われていくことになるのです。
中学・高校時代に学校生活の中での成功体験の機会を奪われると、この時期に学校での様々な人間関係を通して身につけるべき社会経験を一切せずに大人になってしまうことになり、その後の人生にも大きな影響を及ぼしかねません。
【参考文献】
・『不安障害の子どもたち』(近藤直司 編著,合同出版)
・『子どもの心の診療シリーズ4 子どもの不安障害と抑うつ』(松本英夫/傳田健三 責任編集,中山書店)
SADの生徒対応で気をつけるべきこと
授業中に指名して発言をさせるなどの行為は、生徒本人の緊張を高めるため、避けるべきです。
指名して発言を求めるだけにとどまらず、大勢の前で話をする機会そのものから遠ざけてあげるという配慮は必要だと思います。
大人の中には、「何度も場数を踏んで経験を重ねれば、そのうち慣れて何ともなくなるはずだ。」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかしSADの生徒の場合、そうはなりません。
SADの生徒の場合、何度も先生に当てられているうちに慣れて平気になるということはなく、むしろ逆に「次も間違えてしまうだろう」「発表しているときに声が震えてしまうだろう」「その姿を同級生たちに見られて恥ずかしい思いをするにちがいない」という不安が生じるのです。これは以前の、緊張してミスをした際の記憶が頭に刻まれているからですが、具体的には脳の扁桃体や海馬の働きによるものです。
SADを発症している生徒の場合は、扁桃体や海馬などが連携することで不安の感情を再現するため、本人が苦手とする状況にいない場面ですら不安を生じるようになっていると考えられます。
そして、SADという病気のメカニズムを理解して、「性格だから仕方ない」とか「場数を踏めば慣れてくる」とかいう判断をしないことが大切なのです。
【参考文献】
・『子どもの心の診療シリーズ 子どもの心の処方箋ガイド』(齊藤万比古 総編集,中山書店)
SAD発症のピークは14歳
SADの生徒は、苦痛を抱えたまま一人で悩むことが多く、専門の医療機関を受診したり、カウンセリングを受けたりせず、放置することが多いようです。
SADの発症のピークは14歳とされていて、自我が芽生え人目を意識し始める年齢でもあります。中2~3年の時期に当たりますが、不登校・ひきこもりの増加のピークとも重なります。
前段でも触れたように、SADは放置されることが多く、そして自然に治るということはありません。放置の期間が長いと、うつ病などを併発して状態が悪化することは珍しくなく、そうなると治療も容易ではなくなります。
これまでのブログでも述べましたが、早期の発見・治療が大切な病気であると言えます。
放置したまま本人が我慢して、たとえば高校受験を受けて合格したとしても、高校に通うことができなくなり中退する生徒もいます。この場合、中学時代にSADを発症していたにも関わらず、本人が一人で問題を抱え込んで、周囲にも黙っていたということですが、現実にこうした生徒は過去にいたのです。私立の進学校に合格しながらも、1年で退学して通信制高校へ転学しました。
【参考文献】
・『図解 やさしくわかる社会不安障害』(山田和夫 監修,ナツメ社)
教室にも入れず、模擬試験も受けられない
中学時代にSADを発症してそのまま不登校・ひきこもりになるケースと、発症していながらも中学は我慢して登校して高校受験後に耐え切れなくなって不登校・ひきこもりになるケースがあります。
中学時代は何とか我慢して登校していたものの、高校入学後に教室にも入ることができず、模擬試験を会場で受けることもできなくなってしまったという生徒もいます。
この場合、本人の話を聞くと中2の終わりぐらいにはSADを発症していたようですが、高校に入ってからはじめて自覚したというケースです。
SADには、対人恐怖、スピーチ恐怖など実に様々な症状がありますが、本人に病気であるという自覚がなく、性格の問題であるとして片付けてしまう傾向が強いようです。そして周囲の大人が、無理矢理に不安や恐怖を克服させるようなことをしないよう注意することが大切です。
生徒本人が受診を拒む場合は、ご家族がご相談を
SADの症状が出ている生徒は、医療機関(心療内科・精神科)の受診を嫌がることも多く、この場合には保護者の方にまず医療機関に行っていただき、ご相談いただきたいと思います。
生徒本人の代わりに保護者の方が専門家のアドバイスを聞くだけで、安心感が得られますし、その様子を見た本人の抵抗感も和らぎます。この場合に注意することは、「治療が必要だ」「治さなければならない」というよりは「アドバイスを聞きに行く」というスタンスで、生徒本人にお話しすることです。
専門家の話を聞くことで、SADという病気に関する理解が深まり、また具体的な治療法についても納得することができるはずです。
また言うまでもないことですが、中学・高校の担任の先生のご理解とご協力をいただくことも必要だと思いますので、とにかく生徒が一人で悩みを抱え込んでしまうような状況を生み出さないことが大切です。
SADの生徒をひきこもり・ニートにしないためにも、初期対応は非常に重要です。
【参考文献】
・『子どもと家族の認知行動療法2 不安障害』(P.スタラード 著、下山晴彦 監訳,誠信書房)
◆【東京】不登校対応の個別指導塾にしおぎ学院 無料教育相談のお申込みはこちら
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)