記事公開日
最終更新日
不登校・ひきこもりと睡眠障害①〔昼夜逆転の仕組み〕
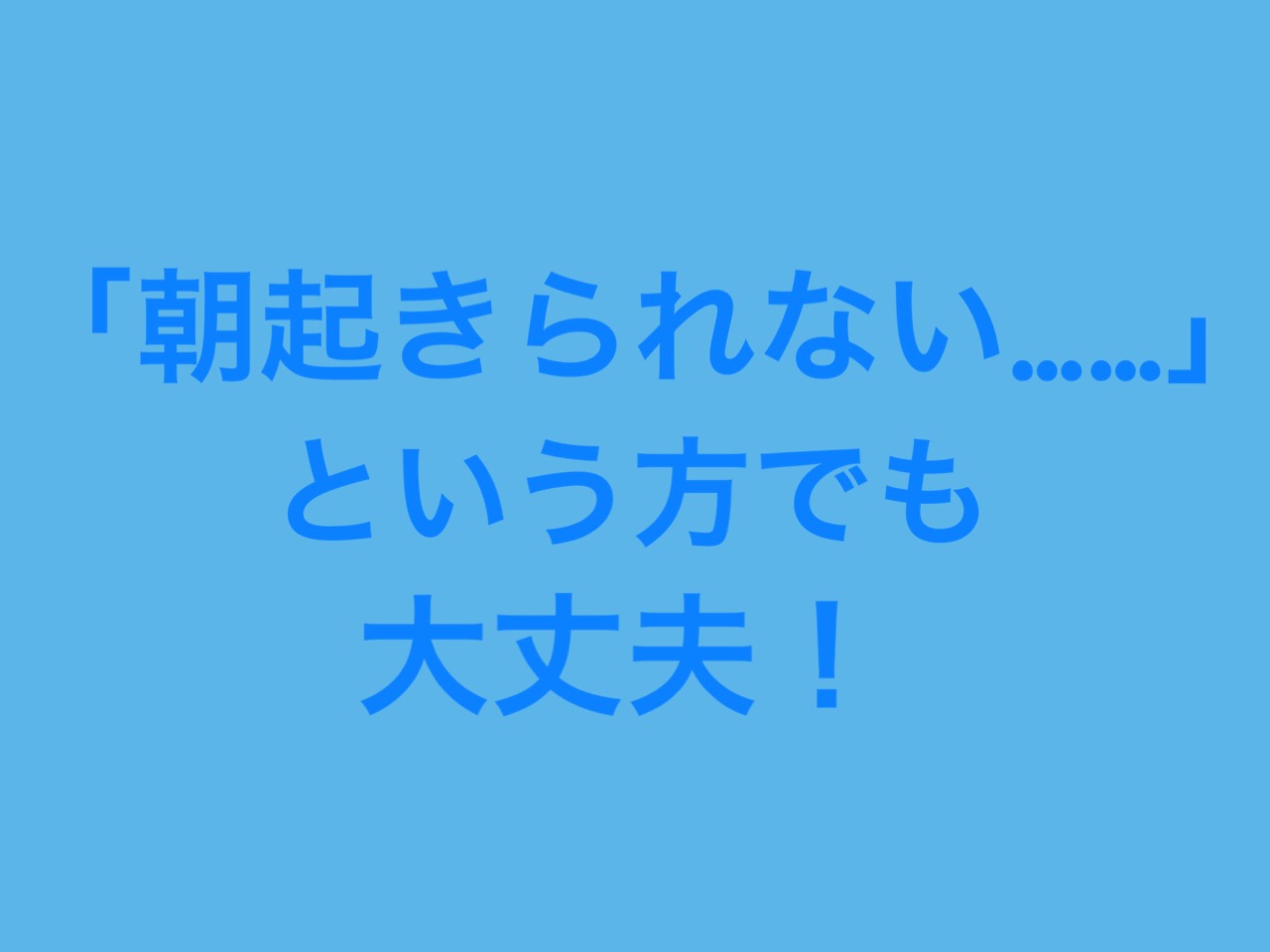
昼夜逆転と不登校について
不登校・ひきこもりと「昼夜逆転」は非常に密接な関係にあります。
ところで、そもそも私たちにとって「昼夜逆転」という現象は不自然なことなのでしょうか。
むしろ「昼夜逆転」は割と簡単に起こりえる現象なのです。そして「昼夜逆転」の生活リズムがいったん固定化すると、不登校・ひきこもり長期化の大きな要因ともなってきます。
今回の記事では「昼夜逆転の仕組み」そのものを、概日リズム、自転周期、ホルモン分泌を基軸に考えていきたいと思います。
1.「早寝早起き」は自然なことではありません
日常的に対応している不登校の中高生の中で、起立性調節障害についで多いのが睡眠障害に悩む生徒たちです。
しかし、どのようにして睡眠障害が引き起こされ、その状態が容易に強化されやすくなるのでしょうか。
そもそも「早寝早起き」という睡眠習慣は自然で当たり前のものだと言えるのでしょうか?
今回は体内時間(生体時間)と24時間周期に焦点化して考えてみたいと思います。
子どもが「夜になったら寝て朝になったら起きるものだ」という睡眠習慣に関する通念は、ヒトの生体時間(体内時計)と地球の自転周期が自然に一致するものであるという前提に由来しています。
後述するように、生物固有の生体時間のことを概日リズムといいます。この概日リズムは生物によって異なると言われていて、ヒトの場合は個人差はあれ約25時間とされています。そして誤差を含めると最大「24時間±5時間」であると言われています。
では一体どのようにして、このけっして小さいとはいえない誤差を調整しながら、私たちは時計によって刻まれる24時間周期に従って毎日の生活を送っているのでしょうか。
2.概日リズムと自転周期はズレています
ヒトの体内時計の中枢は、脳の視床下部にある視交叉上核にあります。
視交叉上核にある生体時計(中枢時計)の周期は24時間よりもやや長く、固有の周期は約25時間とされています。したがって放っておくと次第に時間が後ろにずれていくことになります。
ではなぜ普段は規則正しい生活リズムが保たれているのか。視交叉上核にある固有の中枢時計は普段、外界からの指標(特に太陽光)を手掛かりにして毎朝24時間にリセットして、末梢時計(時計遺伝子)に伝達しているのです。このため毎日、概日リズムとのズレが微調整され規則正しい生活リズムが維持できているのです。
固有の生体周期の方が、地球の自転周期(約24時間)より1時間程度長いために、私たちは容易に夜更かしや朝寝坊ができると考えられています。
しかしその結果として、(大型連休や長期休暇などで)生活のリズムが一度ずれると、意識的に修正をしなければならなくなります。連休最終日まで放置したままにすると、社会生活(中・高生の場合は学校生活)を正常に送る上で支障を来すようになり、不登校・ひきこもりに陥りやすい悪循環が形成されていくのは当然の成り行きなのです。
たとえば、次の日に学校が休みであれば普段より遅くまでゲームをしたりネット動画を見たりしがちです。そして夜更かしした翌日は学校が休みなので普段より遅い時間に起床します。
実はこれだけでも概日リズムと自転周期の大きなズレが生じてしまうことになるわけです。
このズレをリセットしないで数日(場合によっては数週間)過ごしていくと、簡単に昼夜逆転した生活リズムが習慣化し、定着していくことになります。
◆不登校支援ブログ:不登校と起立性調節障害について
3.概日リズムと「ズレ」の修正
地球の自転周期は23時間56分4秒であり、私たちは約24時間の生活リズムで日常生活を送っています。
しかし、生理学者J.アショフの実験により、ヒトには24時間の生活リズムとは別に内在的なリズムが存在していることが分かりました。
生活リズムとは異なる内在的なリズムは通常は約25時間ですが、個体差を考慮に入れると最大で24±5時間と推定されています。
その後、生理学者F.ハルバーグは、この内在的リズムを概日リズム(サーカディアンリズム)と名付けています。
実はこの概日リズムは入眠時刻が約1時間ずつ遅れていくことになります。
私たちは、固有の概日リズムを様々な制約や指標によって毎日、24時間に再修正しているのです。
具体的には、起床時に浴びる朝の太陽光、登校時間や学校の時間割、それらに合わせた規則正しい食事などによって、自らの意思ではなく外界からの刺激や制約によって、私たちは地球の自転周期との時間のズレを修正し続けて生活リズムを維持していると言えます。
言い換えれば、これらの刺激や制約を取っ払って「なすがまま」にしてしまうと、それまで維持してきた生活リズムが簡単に崩されてしまうのです。
4.概日リズムとホルモン分泌の関係
ヒトは毎朝、概日リズムを24時間周期の太陽リズムにリセットして生活リズムを維持しています。固有の概日リズムが25時間であれば、毎朝1時間のズレをリセットしていることになります。
朝になって太陽光を浴びると、このようにしてリセットされた概日リズムから12~13時間は代謝が高められ、体温や血圧も上昇した状態で維持されることになります。概日リズムがリセットされてから14~16時間程度が経過すると、メラトニンという睡眠ホルモンが分泌され始めます。
メラトニンの分泌により、手足の末端から放熱が始まり身体の深部や脳の温度が低下して眠気が生じることになります。
メラトニン分泌は深夜にピークに達しますが、やがて分泌量は減少していき翌朝には全く分泌されなくなります。
そして起床時間を迎えることになるわけです。
5.《睡眠・覚醒》とホルモン分泌の関係
体内では2種類のホルモンが約24時間周期で変化しています。一つはメラトニンです。
前述したように、メラトニンは眠りを起こさせるホルモンで、睡眠中、深夜に向かって血中濃度が最大となっていきます。
もう一つはコルチゾールという覚醒に関係するホルモンです。メラトニンとは逆に、起床時に向かって血中濃度が上昇し、朝6時ごろにピークを迎えます。
規則正しい生活リズムが維持されている場合、概日リズムの進行に従って、睡眠や覚醒を促すそれぞれのホルモンが一定の時間帯に規則正しく分泌されているのです。
睡眠と覚醒をコントロール2種類のホルモンによって、私たちは概日リズムと自転周期のズレをリセットして毎日の生活リズムを保っているのです。
6.次回は「概日リズム睡眠障害」を取り上げます
最初に触れたように概日リズムは通常、自転周期より1時間ほど遅れているため、大型連休や長期の休みなどによって簡単に生活リズムは乱れてしまいます。
つまり「早寝早起き」という生活リズムは、個人の意思というより外的な様々な制約の中でかろうじて保たれている周期に過ぎないとも言えます。
私たちが「当たり前だ」と思っていることは実は全く当たり前のことではないということを理解した上で、昼夜逆転している子どもに接するべきなのです。
地球の自転周期に合わせたこの24時間周期に、実は私たちが固有の生体リズムを適合させていることで成立しているのだといくことを、先ず知っておく必要があるでしょう。
次回の記事では、概日リズムと24時間周期のズレが解消されなくなった過程で発症する「概日リズム睡眠障害」について詳しく見ていきたいと思います。
この記事の最後に参考文献を挙げておきますので、睡眠や睡眠障害について詳しく学ばれる上で参考にしていただけると幸甚です。
【参考文献】50音順
・学校で知っておきたい精神医学ハンドブック(高宮静男著,星和書店)
・小児科臨床ピクシス14睡眠関連病態(五十嵐隆総編集,中山書店)
・睡眠の科学(櫻井武著,講談社)
・睡眠障害の子どもたち(大川匡子編著,合同出版)
・好きになる睡眠医学《第2版》(内田直著,講談社)
◆不登校・ひきこもりと睡眠障害②〔一斉休校と概日リズム睡眠障害〕


