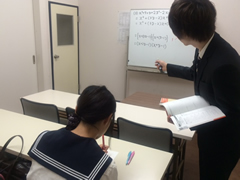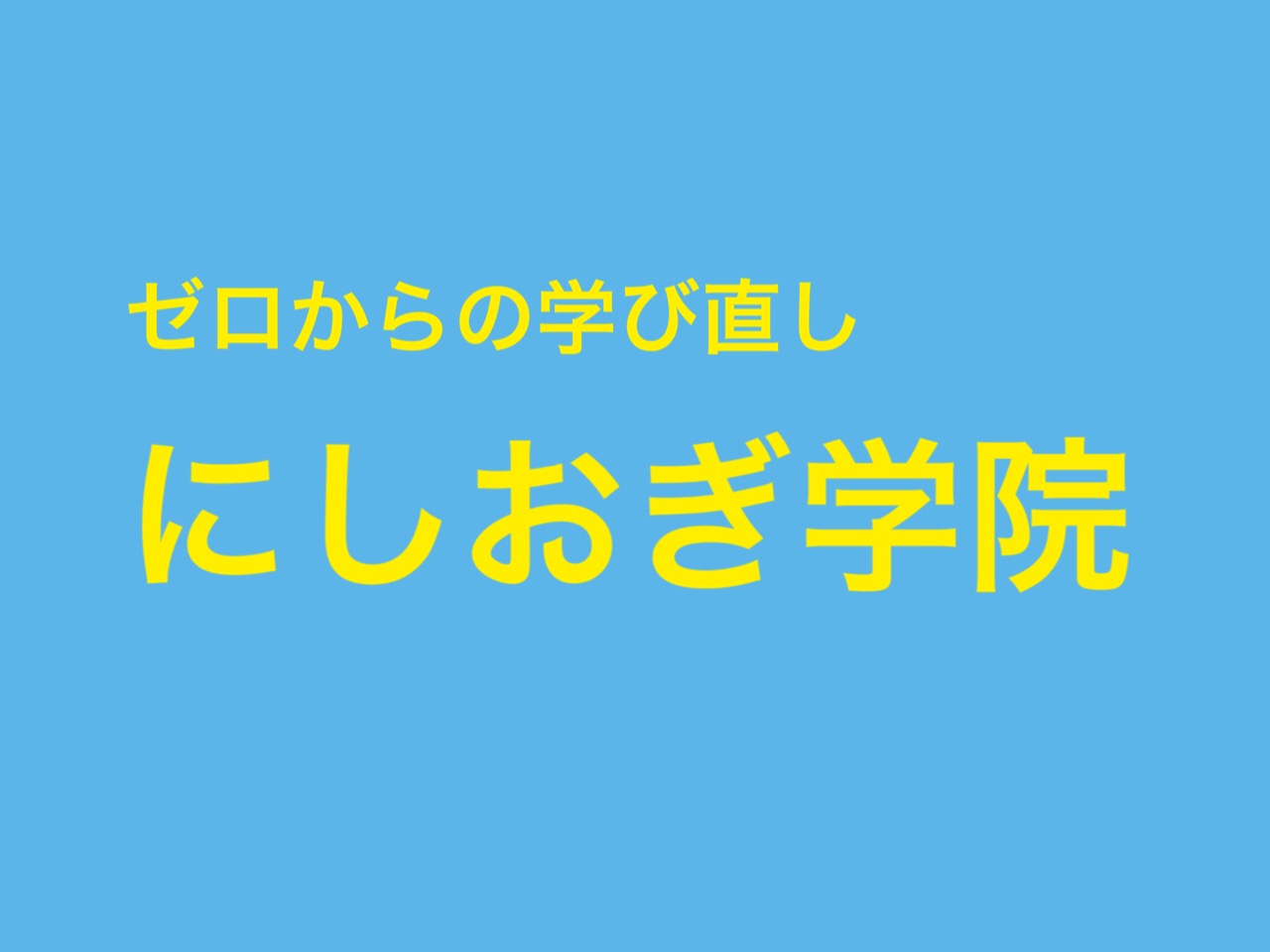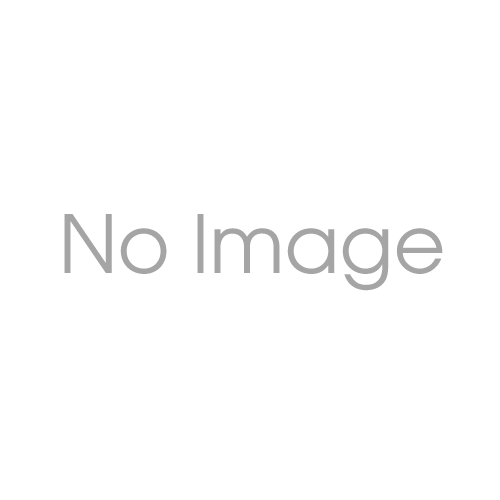不登校・ひきこもりと発達障害⑥〔発達障害における進路選択〕
管理者用
不登校・ひきこもりの4人に1人が発達障害と言われています
不登校・ひきこもりを呈する児童・生徒の中に、発達障害の割合が高いことが分かってきています。
また発達障害と診断されている児童・生徒での不登校・ひきこもりの割合は、そうではない場合の約20倍であるとさえ言われています。
ここで、「不登校」と「ひきこもり」の用語の使い分けについて簡単に触れておきたいと思います。
「不登校」と言った場合、義務教育期間~高校在学期間における社会的ひきこもりを指すのが一般的で、「ひきこもり」と言った場合は青年期以降の社会的ひきこもりを指します。
こううした不登校・ひきこもりのいずれの現象においても、何らかの形で発達障害という診断を受けている人が、約25パーセント含まれていることが分かってきています。そして発達障害をベースとして他の精神疾患が併存していることも少なくありません。
発達障害は他の精神疾患を併発するリスクが非常に高いと言われています。
《参考文献》
・『発達障害が引き起こす不登校へのケアとサポート』(学研:齊藤万比古 編著)
・『小児科臨床ピクシス⑮ 不登校・いじめ その背景とアドバイス』(中山書店:平岩幹男 専門編集)
不登校支援と発達障害について
これまでの不登校支援は、発達障害の関与しないものを前提として考えられてきたという経緯があります。
こうした経緯のため、発達障害のある児童・生徒にとっては、適応指導教室や民間のフリースクールのような、不登校の児童・生徒に居場所を提供するという機関が、必ずしもふさわしいと感じる場所ではなかったとも言えます。
こうした不登校支援機関の特徴をあくまでざっくりと次の3点に集約できるでしょう。
①集団行動への参加は強要せず、あくまで本人の意思による自由参加
②その場にいる時間は好きなことをしていい
③いつ来ても帰ってもいい(入退室自由)
発達障害の児童・生徒にとっては、こうした自由度の高さ、敷居の低さは、かえって分かりにくく、何をどうすればいいのかが分からずに、結局、行かなくなってしまうということも少なくないようです。
発達障害のある児童・生徒の不登校の場合、既存の不登校支援の枠組みに加えて、特別支援教育の知見をもそこに導入する形で複合的に行われていく必要があるのでしょうが、なかなか、そううまくは行っていないのが現状のようです。
《参考文献》
・『最新 子どもの発達障害事典』(合同出版:原仁 責任編集)
・『改訂第2版 小児科臨床ピクシス② 発達障害の理解と対応』(中山書店:平岩幹男 専門編集)
高校進学後も解消されない不登校の再発リスク
そして、中学時代に発達障害を背景に不登校を経験した生徒が、通信制高校や定時制高校に進学した場合にも、生徒それぞれに固有の問題が生じるリスクそのものが解消されるわけではありません。
近年、通学型の通信制高校も増加していますが、結局、通学困難な状況が改善されるどころか悪化して、再び不登校の状態に戻ってしまうケースも多々見られます。
通信制高校の場合、卒業に必要な単位を取得するために、所定のレポートを消化して単位認定試験を受けていかねばなりません。
しかし通学型の集団教育の教授システムに適応できず、再び中学時代のように不登校に陥ってしまった場合、すべてのレポートを自力で仕上げて期日までに提出しなければならなくなります。通信制高校に進学前に不登校期間が長かった生徒にとっては、いきなり集団授業に出席し続けるということは苦痛でしかないことが珍しくありません。
自分で段取りを組んだり、スケジュールを自己管理したりするのが苦手な発達障害のある生徒の場合、こうした自己管理型・自己責任型の通信教育のシステムがいかに困難を強いるものであるかは想像に難くありません。
《参考文献》
・『高校生の発達障害』(講談社:佐々木正美/梅永雄二 監修)
・『小児科臨床ピクシス⑮ 不登校・いじめ その背景とアドバイス』(中山書店:平岩幹男 専門編集)
不登校・ひきこもりの進路選択について
発達障害のある生徒の場合、通信制高校に進学する場合は、その授業システムなどについてしっかりと理解して、進学先を選択する必要があります。
集団型の教授システムが苦手、同年代の友人のグループを作るのが苦手など、本人の特性をしっかりと把握した上での進路選択が大切になってきます。
「楽に卒業できる」というような趣旨の謳い文句にのみ惹かれて入学してしまうと、その後が大変なことになってしまいます。
レポート指導については、ある程度の個別対応をしてくれるような高校を選んだ方が安全だと言えます。
進路先として通信制高校をご検討の際には、発達障害の認知・行動特性への正確な理解とふさわしい配慮のある教職員スタッフがいることが、重要なポイントになってくるでしょう。
《参考文献》
・『発達障害がある子どもの進路選択ハンドブック』(講談社:月森久江 監修)
・『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』(河出書房新社:鈴木慶太 監修)
◆【通信制高校からの学び直し】にしおぎ学院:大学受験コース案内
不登校・ひきこもりからの通信制高校選び
発達障害や、その二次障害(不安障害、うつ病)などの理由で不登校に陥って、通信制高校に入学することを余儀なくされてしまったようなケースでは、いきなり週4~5日午前中に通学して、教室で一斉授業を受けるということは、不登校を悪化させる契機にもなりかねません。また通信制高校の《通学コース》では午前中から授業が開講されることが一般的です。
このため睡眠障害や起立性調節障害、ゲーム障害などを併発している場合には、朝から起床して規則正しく通学すること自体が不可能に近いといわざるを得ません。
この状況で不登校が再発して常態化してしまうと、卒業単位を取得するのもかなり困難な状況になります。
もしこうした状態で高校中退ということになれば、不登校の固定化に発展し、社会的ひきこもり、そしてやがてはニートの状態に陥る危険性も増大していきます。
発達障害があると診断されたり、二次障害を併発してしまっているような状況で、不登校を呈している場合は、特に通信制高校に進学の際に、以下の3点には十分な注意を払っていただくようお願い致します。
ここで進路選択をいい加減に決定してしまうと、取り返しのつかないことになる危険性もあるということです。
①本人が週4~5日通学して、集団型一斉授業に出られるかどうか
②通学困難な場合、レポート作成などで個別対応をしてくれるフォロー体制が整っているかどうか
③発達障害や二次障害を背景とした不登校・ひきこもりの生徒に対して十分な理解・配慮が教職員にあるかどうか
おびただしい数の通信制高校がありますが、選ぶ際には慎重にご検討いただきたいと思います。うちの生徒さんで通信制高校を2回も転学された人もいますので、くれぐれもご注意ください。
◆不登校・ひきこもりと発達障害①~⑩〔不登校支援ブログ一覧〕
★にしおぎ学院から《求人募集》のお知らせです
にしおぎ学院では、発達障害と不登校の問題についてご理解とご関心をお持ちの、大学生のアルバイトスタッフを募集しています。
にしおぎ学院は、個室制のマンツーマン個別指導を行っています。
このため他の個別指導塾のように、講師1名に対して生徒が2名以上になるようなことはけっしてありません。
【歓迎】
・大学1年生(未経験者)の方
・大学で心理、教育、福祉を現在学ばれている方
・特別支援教育や臨床心理学、発達心理学を大学で現在ご専攻中の方
・通信制高校やチャレンジスクール、新宿山吹高校ご出身の方
にしおぎ学院は、JR西荻窪駅から徒歩2分、東京女子大学善福寺キャンパスから徒歩15分以内の便利で落ち着いた場所にあります。
にしおぎ学院のある西荻窪は、吉祥寺と荻窪に隣接する閑静な住宅街です。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております!!
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)