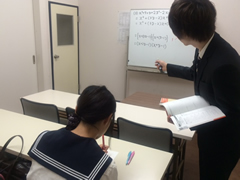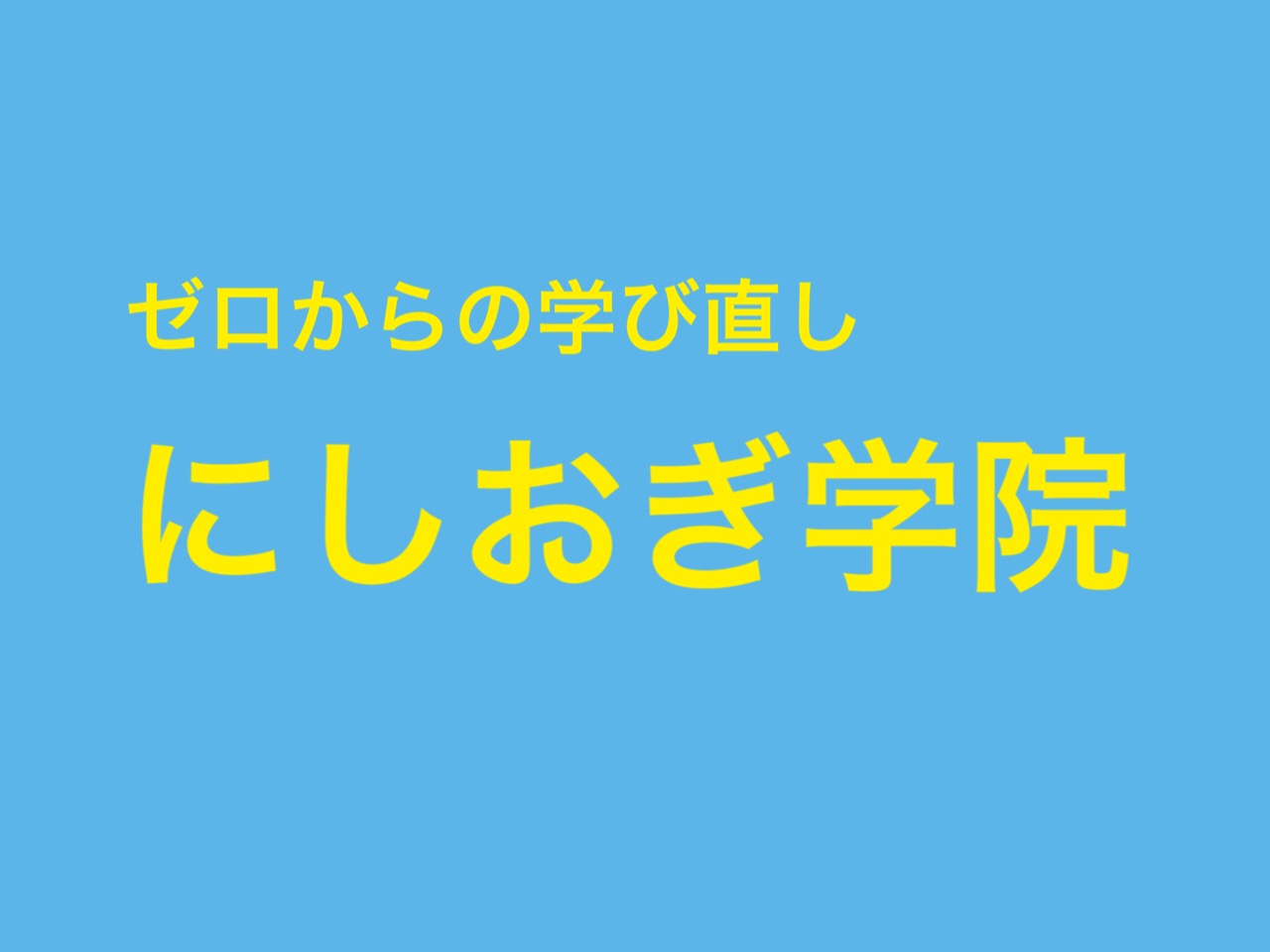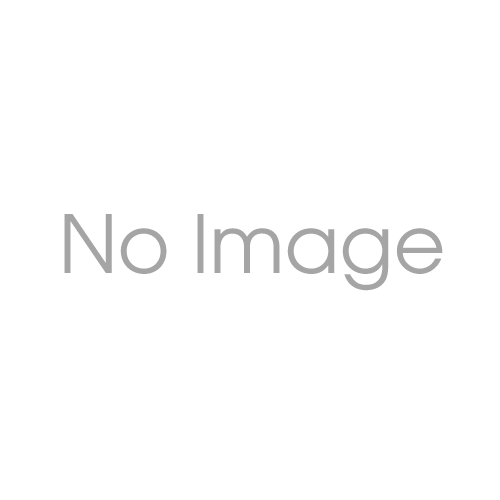不登校・ひきこもりと発達障害⑦〔認知・行動特性について〕
管理者用
発達障害の二次障害を防ぐために
これまでのブログでも述べてきましたが、発達障害において二次障害が引き起こされると、不登校・ひきこもりの状態に発展し、その状態が長期的に固定化していくリスクが増大します。
発達障害の子どもは、その行動特性から再三にわたり親や教師から叱責され非難されている可能性があり、常に怒られ注意され続けると、自尊感情、自己肯定感情を抱きにくい状態になってきます。
こうして自己評価はどんどん低くなり、自分の周囲で起こることをネガティブに捉え続けるようになりますが、この状態がさらに悪化すると二次障害としてうつ病を発症することにもなりかねません。
また、自己評価の低い状態で学業不振になり勉強嫌いになると、学校での授業への関心は薄れ、義務教育を終えて高校に進学した場合、単位未修得のため留年や中退の危機に直面することになります。高校での学業不振は、大学進学にも影響を及ぼすことになりますし、かりに学力選抜を経ずにAO入試などで大学に進学を果たしたとしても、大学卒業は厳しくなる恐れがあります。
スモールステップで自己肯定感を育む
発達障害の子どもは周囲の大人たちから叱責されて育つことが少なくありません。スモールステップでゆっくり歩みを進めること、そして小さな自己肯定を大人たちが促していくことが必要です。
他の子どもと比較したり、否定的な言葉を浴びせることはかえって逆効果なのです。
自己否定的な感情が中核を占めるようになると、自分や将来のことに対してネガティブな感情を抱く傾向が強化されていくことで認知の歪みが生じやすい状態になりかねません。
認知の歪みが生じやすくなると、うつ病や不安障害の発症リスクも大きくなりますし、場合によっては取り返しのつかないことになってしまいます。
どんな小さな成功体験であっても、地道に積み上げ、そしてその都度賞賛してあげることが周囲の大人たちには求められます。頭ごなしに否定することで問題が好転することはありえないのです。
発達障害への無理解が不登校を引き起こします
義務教育の期間とは異なり、高校以上となると、発達障害のある生徒への支援体制が整っているとは到底言い難いというのが現状ではないでしょうか。(いうまでもなく、大学などの高等教育機関においては皆無に等しいといっていいでしょう。)
かりに全日制普通科高校などにそのまま進学してしまったようなケースでは、過度の負担を強いられることになり、そのストレスに押しつぶされてしまうことも珍しくはありません。
高校で履修すべき科目数は、中学までのそれとは比較にならない分量になるからです。中学までは何とかかろうじて乗り切って高校に進学したとしても、高校で要求される学習量を消化できるとは限りません。
できることとできないことの差が激しく、いろんなことを万遍なく行うことが苦手な場合などは、特に早い段階で二次障害を引き起こし抑うつ状態になってドロップアウトしてしまう危険性もあります。そして高校での人間関係は、中学時代に輪をかけて複雑化していきますし、そうした人間関係におけるストレスも、発達障害のある生徒にとっては相当な負担になってきます。
発達障害の二次障害を防ぎ、不登校・ひきこもり・ニートの固定化を回避するためには、発達障害の行動特性について、周囲の理解が非常に重要になってきます。
主な発達障害の分類について
発達障害には、いくつかの分類がありますが、ここではDSM-5に従い、主なものとして「自閉症スペクトラム障害(ASD)」、「注意欠陥多動性障害(ADHD)」、「学習障害(LD)」を取り上げたいと思います。
アメリカ精神医学会が作成する「精神疾患の分類と診断の手引き(DSM)」は2013年5月に改訂され現在第五版(DSM-5)となっています。DSM-5においては、広汎性発達障害(PDD)という名称がなくなっています。
DSM-5に先行するDSM-ⅣーTRにおいては、広汎性発達障害(PDD)と、その下位分類であった自閉性障害、アスペルガー障害(症候群)、特定されない広汎性発達障害がなくなり、これらすべてをまとめて一つの連続体(スペクトラム)として捉え直し、「自閉症スペクトラム障害(ASD)」としてまとめました。
DSM-5では新カテゴリーとして、神経発達障害群が立てられ、その中に、「自閉症スペクトラム障害」、「注意欠陥多動性障害」、「学習障害」などが含まれていることになります。
またDSM-5では、それまでは認められなかった上記の診断名の併存が認められることになっています。これは、現実に発達障害(正式には神経発達障害)においては、ADHDとLD、ASDとADHDなどのように、一人の子どもが複数の診断名に該当することが多いためです。
《参考文献》
・『最新 子どもの発達障害事典』(合同出版:原仁 責任編集)
・『自閉症スペクトラム障害の診断・評価 必携マニュアル』(東京書籍:S.A.ソールニア/P.E.ヴェントーラ 著)
・『学校関係者のためのDMS-5』(医学書院:高橋祥友 監訳)
発達障害の認知・行動特性について
発達障害には特徴的な認知特性があり、これは脳の情報処理機能の特徴・傾向に基づくもので、この認知特性は行動特性として顕在するのが普通です。主な発達障害の認知・行動特性をまとめると以下のようになります。
①自閉症スペクトラム障害(ASD)
・コミュニケーションの障害
・社会性の障害
・興味や活動の限定
②注意欠陥多動性障害(ADHD)
・不注意
・衝動性
・多動性
③学習障害
・読む、聞く、話す、書く、計算する、推論するなどの知的機能のうち一つ以上の領域に遅滞がある
①の自閉症スペクトラム障害ですが、かつてはこの中でも、知的な遅れがないものを高機能自閉症、人との関わり方に関する障害が比較的軽度なものをアスペルガー症候群と呼んでいました。
次回以降のブログでは、①~③の認知・行動特性についてさらに詳しく述べていきたいと思います。
《参考文献》
・『データで読み解く発達障害』(中山書店:平岩幹男 総編集)
・『子どもの発達障害と支援のしかたがわかる本』(日本実業出版社:西永堅 著)
・『自閉症スペクトラム辞典』(教育出版:日本自閉症スペクトラム学会 編)
◆不登校・ひきこもりと発達障害①~⑩〔不登校支援ブログ一覧〕
【求人】発達障害と不登校の問題にご理解ご関心をお持ちの皆さんへ
にしおぎ学院では、発達障害と不登校の問題にご理解ご関心をお持ちの、大学生のアルバイトスタッフを募集しています。
にしおぎ学院は、完全個室制のマンツーマン個別指導を行っています。
このため他の個別指導塾のように、講師1名に対して生徒が2名以上になるような状況はけっしてありません。
【歓迎】
・大学1年生(未経験者)の方
・大学で心理、教育、福祉を現在学ばれている方
・特別支援教育や臨床心理学、発達心理学を大学で現在ご専攻中の方
・通信制高校やチャレンジスクール、新宿山吹高校ご出身の方
にしおぎ学院は、JR西荻窪駅から徒歩2分、東京女子大学善福寺キャンパスから徒歩15分以内の便利で落ち着いた場所にあります。
にしおぎ学院のある西荻窪は、吉祥寺と荻窪に隣接する閑静な住宅街です。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております!!
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)