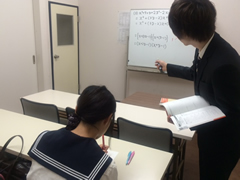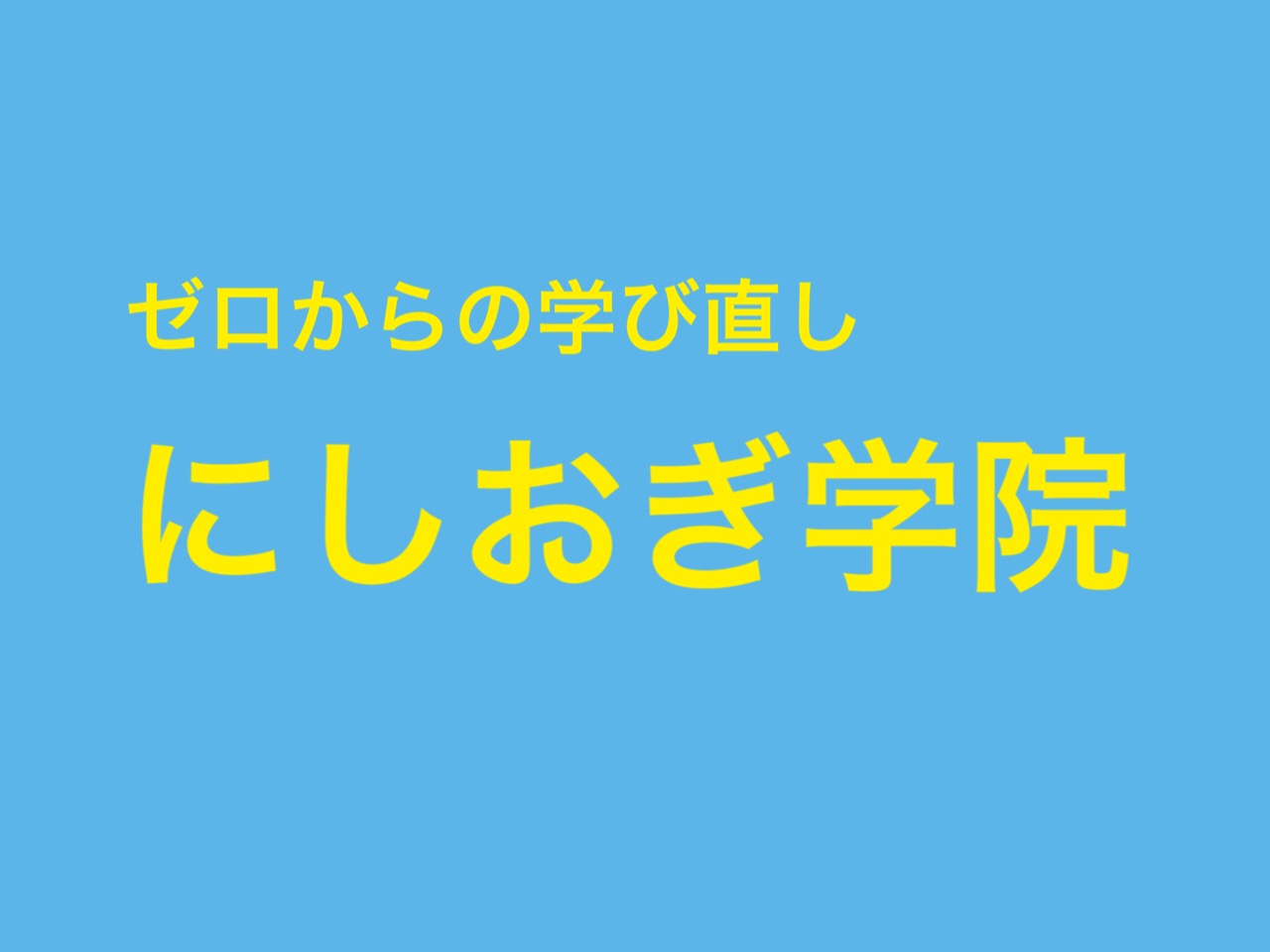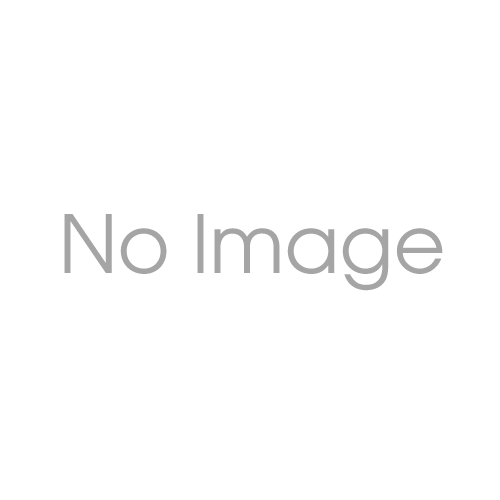不登校・ひきこもりと不安障害について①〔不安障害の分類〕
管理者用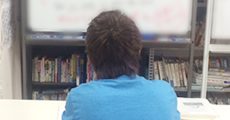
不安障害と不登校・ひきこもりについて
不登校・ひきこもりは、児童・思春期の心の問題として、最近増加の一途を辿る一方で、今や珍しくなりつつありますが、明確な判断基準では捉えきれない曖昧さを持っています。
しかし、不登校という言葉を考えていく上で、「不安」を切り離して考えることはできないでしょう。もちろん不登校の生徒たちすべてが不安障害であるとは言えないにせよ、「不安」という心的現象を完全に排除することは逆に難しいのではないかと言えます。
したがって、不登校やひきこもりに悩み苦しんでいる生徒たちの気持ちを理解していくためにも、こうした生徒たちが抱える「不安」とは具体的にどのようなものなのかを、できるだけ深く知っておく必要があるのではないでしょうか。
このブログでは、不登校・ひきこもりを引き起こしている不安障害を、精神医学的知見に基づいて把握していきたいと考えています。
児童・思春期における不安障害としては、分離不安障害、社会(社交)不安障害、全般性不安障害、強迫性障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などが中核を占めると考えられます。
これまでのブログ記事でも触れてきましたが、認知行動療法の方法論的な立場からは、環境・出来事に対する危険への歪んだ認知によって、不安障害が起こっているとされています。そして、この認知行動療法による歪んだ認知の修正がきわめて有効であると言われているのです。〔参照⇒不登校・ひきこもりと認知の歪み①〕
【参考文献】
・『子どもの心の診療シリーズ1 子どもの心の診療入門』(齊藤万比古 総編集・責任編集,中山書店)
・『子どもの心の診療シリーズ4 子どもの不安障害と抑うつ 』(松本英夫/傳田健三 責任編集,中山書店)
不安障害の分類
不安障害を分類した場合、おおむね下記のようになります。不登校・ひきこもりの生徒の保護者の方の中には、これらをお読みになって、お心当たりがあると思われる方も少なくないと思います。
①分離不安障害:その子にとって最も愛着のある人(主に母親)や家族からの分離に対する過剰な不安を基本症状としています。
②社会(社交)不安障害:人前で、自分が他者からの注視を浴びているかもしれない状況、持続的な恐怖感を抱き、こうした恐怖刺激によって不安感情が誘発され、その結果、社会的な状況からの回避を引き起こしてしまう障害です。
③全般性不安障害:慢性的に漠然とした不安が持続している障害です。
④強迫性障害:強迫性障害は、頻発する強迫観念(持続的な考えや心象)、もしくは強迫行為(特定の行為・儀式を行う)によって規定される障害です。
⑤パニック障害:強い不安や恐怖により、自律神経症状を中心とする発作(動機・混乱・めまい・吐き気・呼吸困難)が突然に出現し、わずかな時間で消失するという特徴の障害です。
⑥心的外傷後ストレス障害:激しい児童虐待や体罰、いじめなど、重大かつ苛烈な身体的・精神的外傷を体験した後に生じる不安・恐怖などの精神・生理的な反応群です。
※アメリカ精神医学会によって出版されている『精神障害の診断と統計マニュアル』第5版〔DSM-Ⅴ〕(2013)では、強迫性障害と心的外傷後ストレス障害は、不安障害の下位分類ではなく、不安障害と同等の大項目として分類されています。
【参考文献】
・『学校関係者のためのDSM-5』(高橋祥友 監訳,医学書院)
不安障害は誰でも罹る可能性がある
「不安」と言っても、健康な人にも当然ながら生じるものであって、「不安」が生じるからと言ってそれだけで病気であるとか障害であるとか言えないことは言うまでもありません。
不安障害の人の「不安」は、性質においても強度においても、健康な人とは大きく異なります。そのため、日常生活や学校生活に大きな支障を来たす結果になり、不登校やひきこもりにいたることにもなってしまうのです。
しかし近年の研究によれば、不安障害は、健康な人の心理の延長線上にあり、連続的に移行しているものであるとされています。したがって、その意味ではどの児童・生徒でも罹る病気であると言えます。
不安障害は、いわゆる「精神病」ではありません。大きな身体的病変によるものではなく、その児童・生徒の悩みや苦しみは、理解可能なものであると言うことができます。
【参考文献】
・『不安障害の子どもたち』(近藤直司 編著,合同出版)
一概には言えない不安障害の要因
不安障害は、これまで心理的要因によってのみ生じると考えられてきましたが、体質的要因、社会文化的要因などが複雑かつ相互に関与して起こることが明らかになってきています。そして、どの要因が強く働いているかについては、個人によって様々であるようです。
また最近の研究では、うつ病と不安障害、そして発達障害の関連についても併存しやすい病態であると言われており、AD/HDなどにおいても最も併存しやすい病態が、うつ病や不安障害であるとされています。
今後のブログでは、不安障害や抑うつによって不登校・ひきこもりにいたってしまった生徒の状況について、個々に検討していきたいと思います。またその際には、これまで依拠してきた認知行動療法によって得られた知見を適宜参照していきたいと考えています。
不登校・ひきこもりの長期化が問題になっており、特に通信制高校卒業生の45パーセントが進路未決定で、進学も就職もしていないということが社会問題化しつつあります。不登校・ひきこもりの長期化、常態化を防いでいくためにも、こうした生徒たちが抱えている「不安」や「恐怖」を早期に発見し、適切な対処法を検討していく必要があると考えています。
【参考文献】
・『臨床児童青年精神医学ハンドブック』(本城秀次/野邑健二/岡田俊 編集)
・『くらしの中の心理臨床④ 不安』(青木紀久代/野村俊明 編,福村出版)
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)