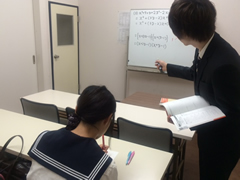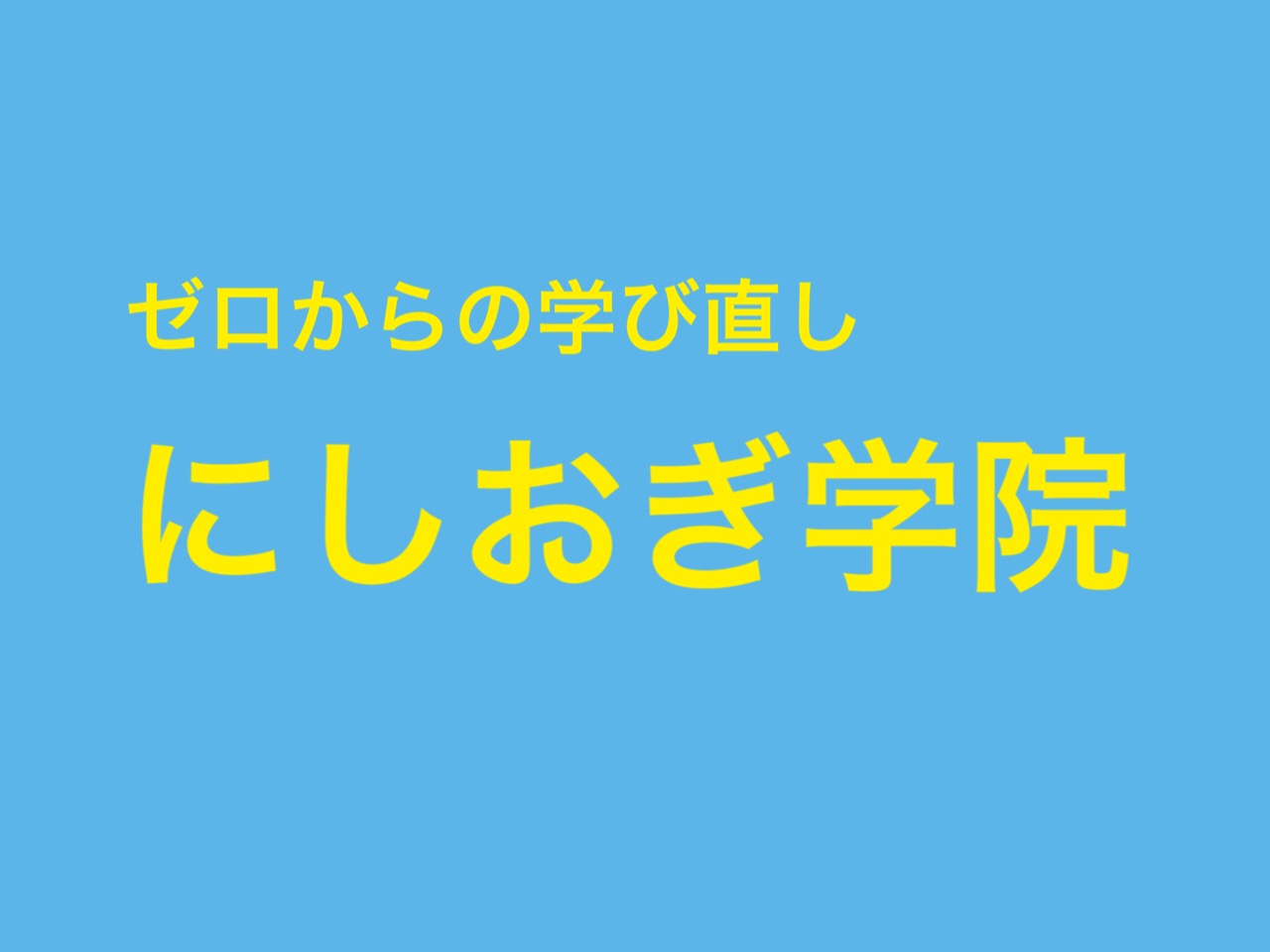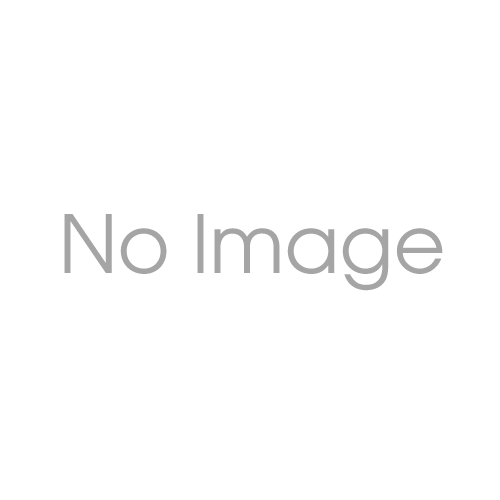起立性調節障害〔OD〕と不登校・ひきこもり⑥【ODからの進路選択】
管理者用起立性調節障害〔OD〕からの進路選択
前回の「起立性調節障害〔OD〕からの高校進学」に続き、ODによる不登校からの進路選択について、さらに深く掘り下げたいと思います。
小中学校は義務教育ですが、中学卒業後からは自ら進路選択を行わなければキャリア形成が途絶される危険性があります。このようなハイリスクな状況にならないようにするためにも、高校に進学すべきか、高卒認定試験を受検するか、あるいはこれらを併用して高卒資格を取得するかを決めていかねばなりません。
にしおぎ学院は不登校学習支援に特化した学び直しの支援や受験指導を行っている個別指導塾です。ODなどの理由で日中通塾できない不登校生のための《夜間授業》も開講しています。
◆不登校支援ブログ:起立性調節障害と不登校・ひきこもり①~⑨まとめ
1.中学卒業後の進路選択とOD
前回のブログでも触れましたが、起立性調節障害〔OD〕を中学時代に発症し不登校が長期化・常態化してしまっているような生徒の場合、高校進学を考える際には進路選択に慎重になる必要があります。
進路選択の際にあまり深く考えずに、「高校に入ったら何とか毎日通えるようになるだろう」と全日制の高校に進学させてしまうと、多くの場合は、毎日通学する体力がなく、大きな負荷が本人にかかることになってしまいます。
出席日数が大幅に不足することで留年が確定してしまった場合に、本人が受ける精神的なダメージは計り知れないものになりかねません。こうした予見可能なリスクについては、進路決定の際に十分に配慮の上慎重な検討をしておく必要があります。思っている以上に、ODは厄介な病気なのです。
2.私立中高一貫校での不登校について
またもう一つ問題になるのは、中高一貫校で、不登校が常態化しているにもかかわらず、そのまま高校に進級させてしまうというパターンです。
中高一貫校では、中学時代に不登校であっても、エスカレーター式に高校に進級できる場合があります。
しかし結局は昼夜逆転した夜型の生活リズムが改善できず、そのままずるずると朝起きられずに遅刻・欠席を繰り返すことになり、留年の危機に直面することになります。
中高一貫校の場合は、ODの経過をいたずらに長引かせてしまうこともあり、高校進級後の留年のケースでは、留年から中途退学に結びつくことが珍しくありません。
中退後には長期間のひきこもり生活に入ってしまうリスクも増大します。
ひきこもりそのものは現実からの逃避行動ではあるのですが、ひきこもり生活が長引くと当事者の自己否定感情を強化し、自罰的な傾向を強くしてしまう恐れがあります。
そうなると、社会復帰することへの不安や恐怖が増大し、ますます回復に時間がかかることになりかねません。
◆不登校支援ブログ:起立性調節障害と不登校・ひきこもり①~⑨まとめ
3.高校選びは、通学の頻度・距離・時間に要注意
中学でODを発症して、ほぼ毎日欠席状態になり自宅でひきこもり生活をしているような場合は、通学制(全日制・定時制)ではなく通信制の高校への進学も選択肢に入れたほうが安全でしょう。
現在の通信制高校には、「通学型」を取っている高校もあり、週1~5日の選択の幅が設定されているはずです。
ここで気をつけるべきことは、毎日、午前中に起きて通学できる体力が本人にあるかどうかということです。
中学時、特に直近の中3時点での出欠状況を目安にして、通学に耐え得る体力を持っているかどうかを慎重に検討しなければなりません。
◆不登校支援ブログ:起立性調節障害と不登校・ひきこもり①~⑨まとめ
4.通学プロセスを具体的にシュミレーションする
通学型の通信制高校を選ぶ際には、所在地や通学距離・時間、通学時間帯の電車・バスの混み具合なども総合的に判断する必要があります。
入学した後の、通学のシュミレーションを事前にしておくことは非常に重要です。「高校に入ったら行けるようになる」というような考えを持っているとしたら、それはとても危険です。慎重のうえにも慎重に検討を重ねておく必要があるでしょぅ。
実際にその高校の始業時間に合わせて通学のシュミレーションを体感しておかねばなりません。入学したはいいものの、その後1日も通学できないのであれば何の意味もありませんし、そこで味わうことになる挫折感は、自己否定感情の助長にも繋がってしまいます。
通学できるかどうか以前の問題として、朝の決まった時刻に毎日きちんと起床できるかどうか、そして仮に何とか通学できたとして午前中に高校の教室で過ごせるかのどうかについて、そもそも考えておく必要があるでしょう。
◆不登校支援ブログ:起立性調節障害と不登校・ひきこもり①~⑨まとめ
5.通学頻度は週1~2日(午後始業が望ましい)
ODが重症なら、週1日の通学がやっとでしょうし、多くて週2日程度が限度ではないでしょうか。週1~2日の通学頻度であっても、できれば始業時刻が午後からの方が好ましいでしょう。
週1~2回の通学頻度であっても、継続的に通学できるようであれば、2~3年で9割程度のODの症状は改善すると言われていますし、高2~3にはODが治ることが多いようです。
注意しなければならないのは、通学できる見込みもないのに見切り発車で週5日制の高校に進学して通えなくなってしまうことなのです。
特に、先程触れた中高一貫校でエスカレーター式に高校に進級してしまった場合、中途退学の可能性が高く、その際の精神的に受けるダメージを考えれば、安全策として通信制高校(週1~2日程度)を選択した方がいいと言えます。
◆不登校支援ブログ:起立性調節障害と不登校・ひきこもり①~⑨まとめ
6.中・長期的なスパンで社会復帰を目指す
適切な治療を受けている場合、不登校・ひきこもりを伴うような重症のODでも、2~3年で社会復帰ができるとされています。
高校への進学の際に、焦って無理のある進路選択をするのではなく、高校2~3年を目安にじっくりと治して大学進学に備えるというスタンスが必要ではないでしょうか。
そうしなければ、治るものも治らないばかりか、症状が悪化してひきこもり生活が常態化してしまう危険性もありますし、最悪の場合、高校で1単位も取得できずにそのまま学籍を失い、なし崩し的にひきこもり生活が長期化してニートになってしまうということにもなりかねません。(現に、そのような生徒はいます。)
結果を焦るのではなく、中長期的なスタンスで少しずつ生活のリズムを取り戻し、ストレスなく勉強に取り組むことのできる環境を作っていくことの方が大切です。焦って極端な負荷をかけてしまうと、心理的なストレスが増大しますし、心理的ストレスはODの症状の悪化を招きます。
焦らずにゆっくりと症状の改善を目指しつつ、地道に中学時代の学び直しを進め、生活リズムを整えながら、将来の大学受験に備えてほしいと思います。
7.日中通塾できない不登校生のための《夜間授業》
にしおぎ学院は、不登校学習支援に特化した個別指導塾です。
起立性調節障害などの理由で日中の起床が難しい不登校生のために、平日20時~21時20分に夜間授業を開講しています。
にしおぎ学院には、主に次のような中学・高校生が通塾してそれぞれの希望進路の実現に向けて勉強に取り組んでいます。
そして毎年、起立性調節障害に悩む多くの中学・高校生たちが自らの希望進路を実現しています。
・都立チャレンジスクールや都立新宿山吹高校〔普通科・情報科〕への進学を志望する中学生⇒高校受験コース案内
・通信制高校、チャレンジスクール、新宿山吹高校の高校1~4年生や既卒生⇒大学受験コース案内
にしおぎ学院への入塾・受講をご希望の方は、無料教育相談フォームにてお問合せください。
◆不登校支援ブログ:起立性調節障害と不登校・ひきこもり①~⑨まとめ
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
Category
- 不登校 (728)
- チャレンジスクール (646)
- 通信制高校 (612)
- 定時制高校 (544)
- フリースクール (235)
- 発達障害 (148)
- 入塾者募集 (117)
- 学習支援 (117)
- うつ病 (99)
- 不安障害 (94)
- お知らせ (84)
- 大学受験 (78)
- 求人 (71)
- いじめ (43)
- ニート (25)
Tags
- 都立新宿山吹高校 (342)
- 都立稔ヶ丘高校 (292)
- 適応指導教室 (273)
- 都立世田谷泉高校 (253)
- 起立性調節障害 (244)
- 睡眠障害 (79)
- 学習障害 (24)
- 適応障害 (14)
- スマホ依存 (13)
- パーソナルスペース (4)